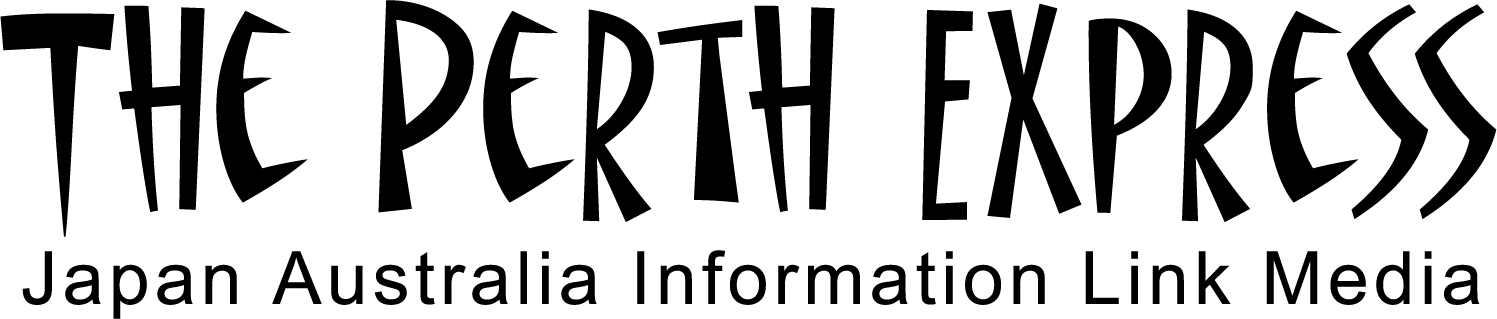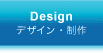|
Vol.166/2011/11
|
第2回 「農家の情熱」 柴田 大輔
 |
収穫の合間に一息つく飛田さん夫妻。「不検出」の検査結果に安堵の表情が浮かぶ(2011年10月)。 |
10月、収穫を迎えた畑で飛田さんと会った。仕事の合間に検査結果について伺った。もしもを考えると、話題を出すことにためらいもあった。しかし、飛田さんの口から「不検出だった」ということを聞く。この検査では、最小で1ベクレルの放射性物質が検出可能だ。この「1ベクレル以下、不検出」は、県が発表する結果よりも詳細である。県による検査では最小が20ベクレルとなる。飛田さんの畑で出た値は、限りなく0に近いといえる。
10月で収穫を終えた芋は、一ヶ月間寝かし、糖度が上がった11月末から干し芋へと加工される。12月から3月にかけ、加工・販売が忙しく続く。ホームページに検査結果を表示し、干し芋販売が始まるころには、店頭に結果を張り出すという。芋を干す「干し場」の表土を削って除染対策もした。全ては、飛田さんを信頼し繋がってきたお客さんのためだ。
命を注いできた畑が、汚されているかもしれない。それを何故、生産者自身が調べなければいけないのか。生産者自身が検査し除染する。こんなやるせないことがあっていいのだろうか。
ある農家の方は、「人の家にゴミをまき散らしたら、持ち主が来て片づけるのは当然だ」、そう声を荒げる。
飛田さんの生産者としての強いプライドが、検査結果をお客さんに示すという行動に表れている。事故の責任者である電力会社・政府は、生産者に甘えている。また、私達消費者は誰のおかげで毎日食卓を囲むことが出来ているのか。これまで無意識に繋がってきた生産者と消費者の絆を、今だからこそ意識したい。
12月の空っ風が吹くころ、ひたちなか市のあちこちで芋が干される。太陽の光を受けた芋たちは、作り手の情熱と、芋自身が持つ生命力をぎゅっと凝縮させ、やさしい甘味をもった干し芋として、一年間待ち続けた人々のもとへと届けられる。
柴田 大輔
1980年茨城県生まれ。フォトジャーナリスト。中南米を旅した後、2006年よりコロンビアを中心に、エクアドル、ペルーで、先住民族や難民となった人々の日常・社会活動を取材し続ける。3.11以降は、故郷の茨城を記録している。
  |