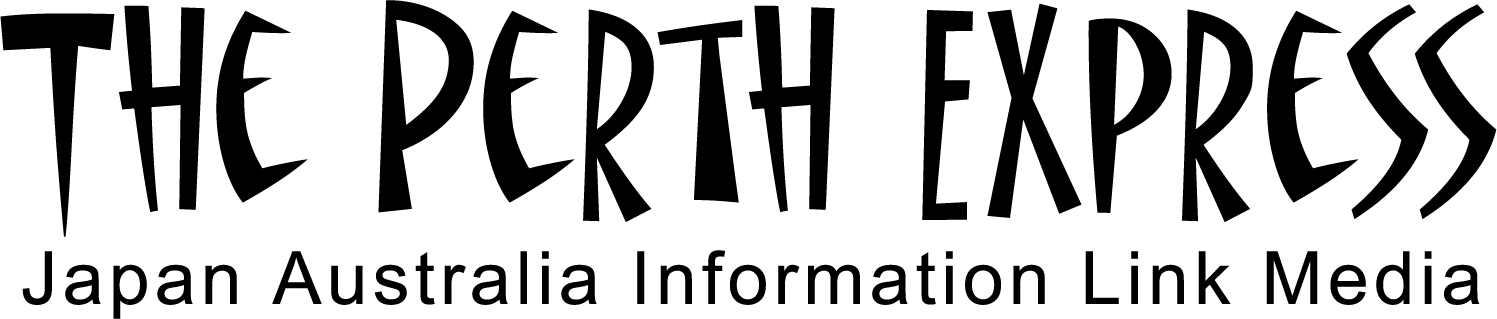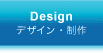|
Vol.190/2013/11
|
「抗いの彷徨(1)」

1990年初めのカリブ海の国ハイチでは、民主的な選挙で選ばれた大統領が国外追放となった。米国ボストンにやってきたハイチ大統領を支援するための集会に集まったハイチ人たち。抗議の拳を上げる。
映画『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』に戻る。社会生活を送くるに当たって、このような数学の法則を理性として理解しても、直截的には役に立たない。人間には感情があるからである。映画の中で、マット・デイモン演じるウィルは天才だとしても、個人としてはやりきれなさを抱え続ける。社会的に賞賛される能力と個人的に傷ついた心の闇は両立しないからだ。一人の青年の心と考え方の変化を追っていく様子をこの映画は描き出していく。まあ、いかにもハリウッド的という映画だと評しても過言ではないが…。
私がこの映画に惹かれるのは、まず第一に、この映画がそのスノビッシュ(snobbish)なボストンを舞台にしているからである。実はボストンといっても、下町ボストンは外から見るほど華麗ではない。つまり、人は外見で判断できないのだよ、という皮肉がこの映画に含まれている。この映画を見ると、自分もその町で90年代前半の一時期、がむしゃらに頑張ったんだな、という感情が湧き起こってくる。生活費を切り詰めながらの実生活の感覚が、今も忘れられない。
さらに、この映画を繰り返し観ていて気づいたことがある。映画の最後、エンドロールにスタッフやキャストなどの名前が出た最後の一瞬、画面が終わる寸前に、次のような文字が現れるのである。
IN MEMORY OF ALLEN GINSBERG & WILLIAM S. BURROUGHS
そう、ジャック・ケルアックではないが、これもビートニクスの雄であるアレン・ギンズバーグとウィリアム・バロウズの2人の名前が記されているのだ。もしかして、マット・デイモン自身がビートニクスか、と思った。だが、そうではなく、どうやらこの映画の監督ガス・ヴァン・サント氏のこの2人のビートニクスに対する思い入れのようでもある。
調べてみると映画『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』の脚本は、マット・デイモンが幼い頃からの親友であるベン・アフレック(俳優・脚本、後に監督)と共同で書いている。しかも、ハーバード大学の学生時代にその原本を書いている。米国でも最も進歩的な町であるボストンで生まれ育ったマット・デイモンとベン・アフレックの両者には、やはりビートニクスの気を感じるのである。
1960年代から80年代初めにかけて、米国はベトナム戦争の影響もあり、国内では強い反戦運動から国家に対して激しい抵抗運動が起こった。「東西冷戦」が世界を覆った。思想や主義主張を基にして、人間の生活や人間性そのものが反故にされ毀損される事態が世界を曇らせた。そこで、人びとは拳を上げて抵抗した。抵抗運動の熱は世界中に広がった。
たぶん、自分もその熱波に冒された一人であろう。今、振り返ると、その時代の雰囲気に浮かれていたかもしれない。不覚にも「自由の国アメリカ」に憧れを抱いてしまった。
だが、90年代も後半になると、時代を覆っていた熱の炎は下火になり、拳を振り上げる抵抗運動も東西冷戦の終結と共に弱まっていった。ある人びとは、闘いに敗れたと感じて社会に背を向けた。ある者は時代に取り残されまいと過剰な競争社会に同調し始めた。そんな中で心の優しき人は傷つきやすく、社会から取り残され始めた(とも錯覚された)。
『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』は、そんな時に生まれ出た映画である。社会に抵抗や闘いを挑むというよりも、傷ついた心身をいたわりながら、どこかしら社会に背を向けようとしている時代にである。この映画には、共同の脚本家であるベン・アフレックも「チャッキー」という親友役で出演している。映画の主人公はウィル扮するマット・デイモンだが、映画の中でベン・アフレックの方も、見る者を唸らせる演技で存在感を十二分に示している。
そんなベン・アフレックはその後、監督としても手腕を発揮し、デビュー作の『ゴーン・ベイビー・ゴーン』や『ザ・タウン』など、ボストンを舞台にハリウッド風のヒューマンストーリーの映画を製作している。
 |